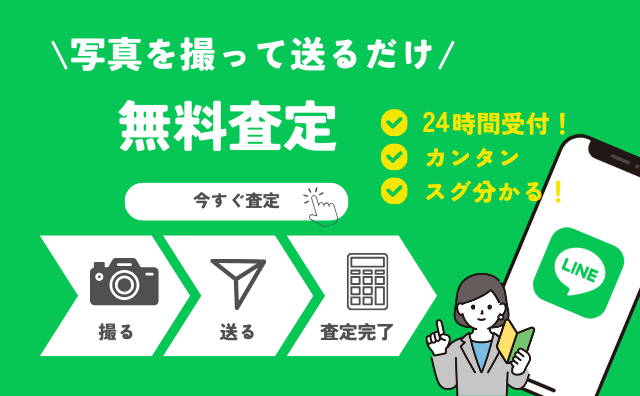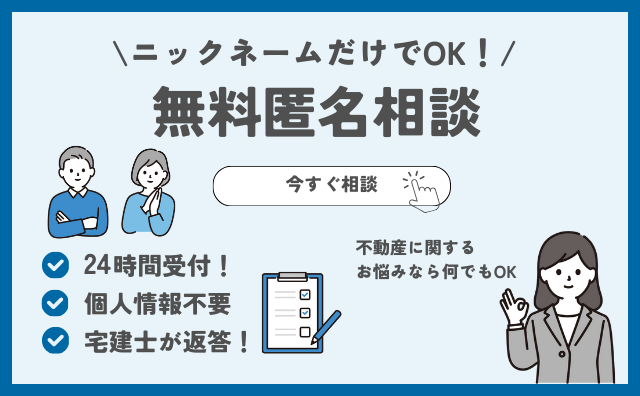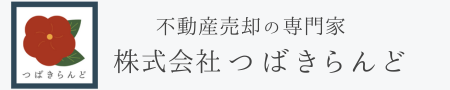維持する
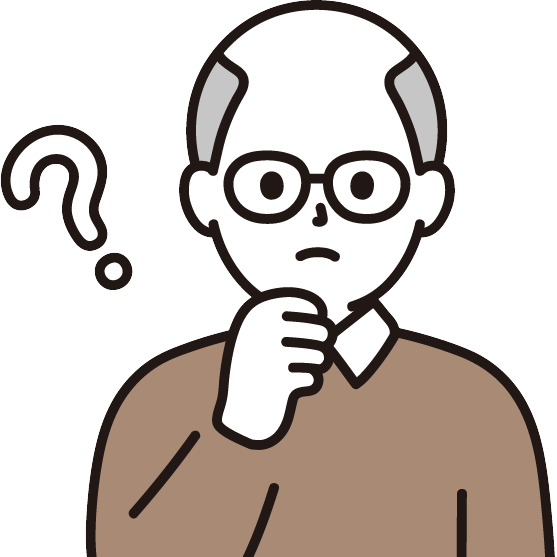
実家を相続したのが、たしか去年の春ごろだったと思います。父が亡くなって、手続きが一段落してから、ずっとそのままになっていて。
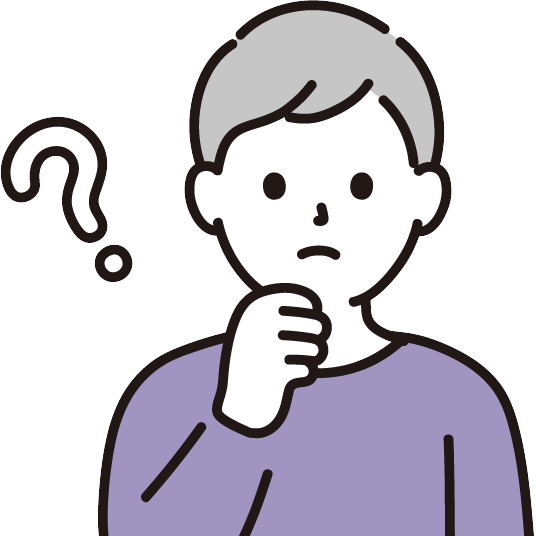
私たちも今は別の場所で暮らしているし、住む予定もないんです。かといって、貸したり売ったりっていうのも、まだ決めきれなくて。
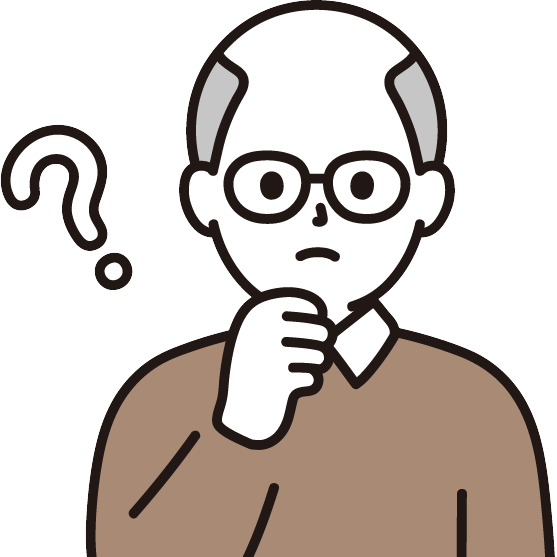
とりあえず、今はそのまま持っておこうかなと考えてるんですけど…。このまま維持していくとなると、なにか注意すべきことってありますか?

そういったご相談はよくありますよ。
経済的な面だけで見れば、売却や活用のほうがメリットは出やすいんですが、簡単に決められないお気持ちもよく分かります。
維持される方向でお考えでしたら、できるだけ負担の少ない方法を一緒に考えていきましょう。
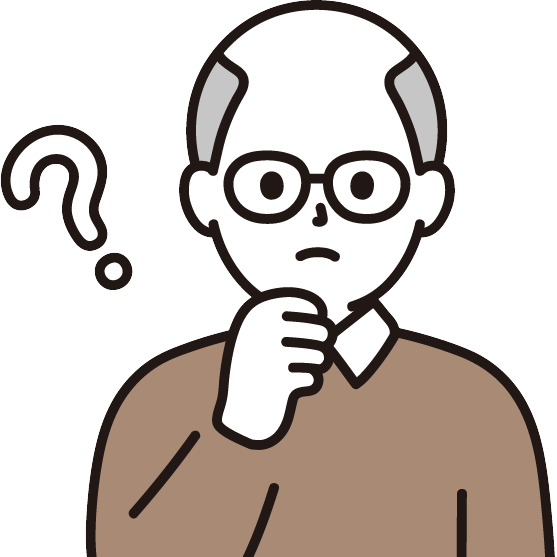
助かります。“このままで大丈夫なのかな”ってずっと気になってて。
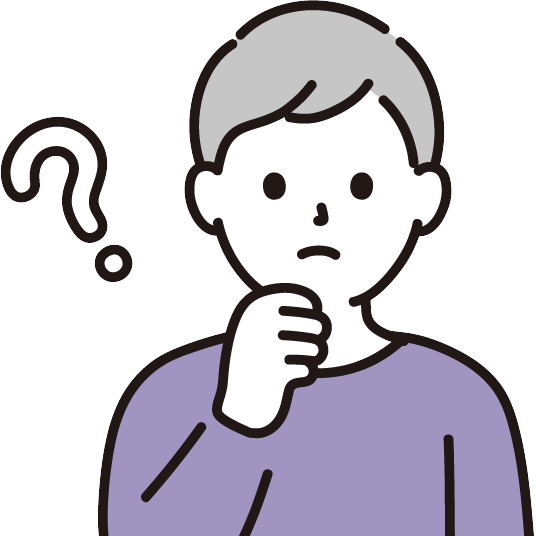
私たち、専門的なことはよく分からないですし…。何から手をつけたらいいのかも、はっきりしなくて。

そうですよね。まずは、“なぜ維持したいと思っていらっしゃるのか”というお気持ちの部分を整理しておくと、今後の判断もしやすくなりますよ。
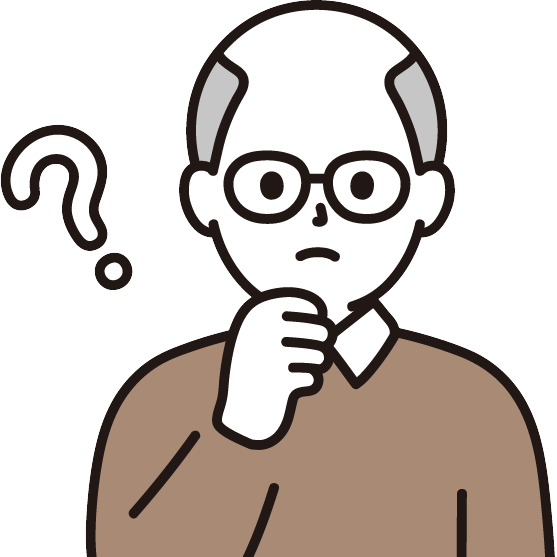
そう言われると…やっぱり父が建てた家だからっていうのが大きいですかね。思い出もあるし、急いで手放すような気持ちにはなれないんです。
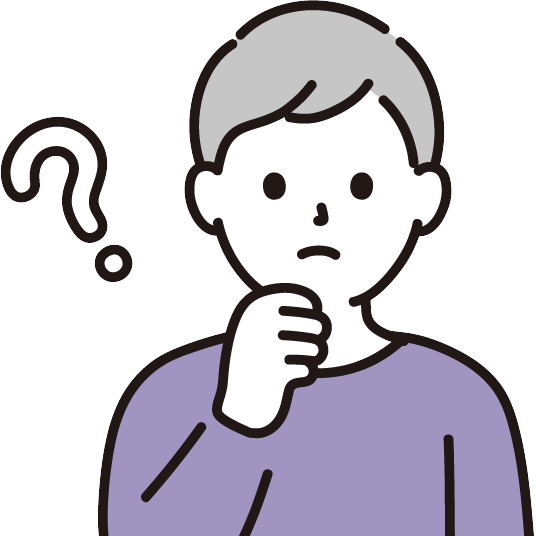
私は、子どもたちがいつか使うことがあるかもしれない、って思うと…もう少し様子を見たいなって。

将来使う可能性があるなら、維持する価値はありますね。ただ、“なんとなく残しておきたい”という気持ちで持ち続けると、思わぬ負担が出てくることもありますので、その点も含めてご説明しますね。
維持するメリット

まずは“維持するメリット”から見ていきましょうか。たとえば、お子さんやお孫さんが将来使う可能性がある場合、残しておく価値はありますよね。
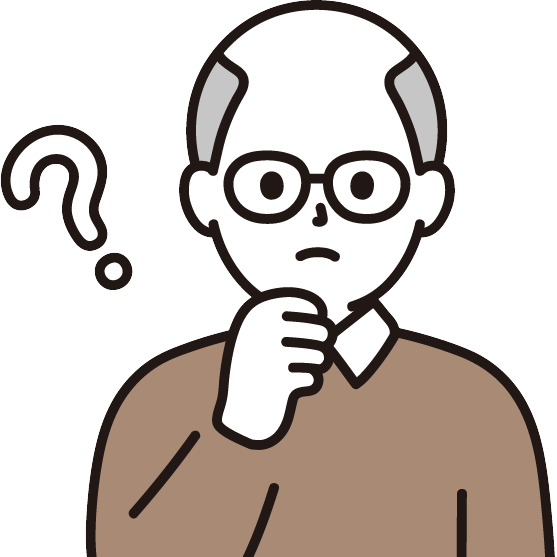
そうですね。息子が“いずれ戻るかも”って言ってたこともありました。まだ先の話だとは思いますけど。
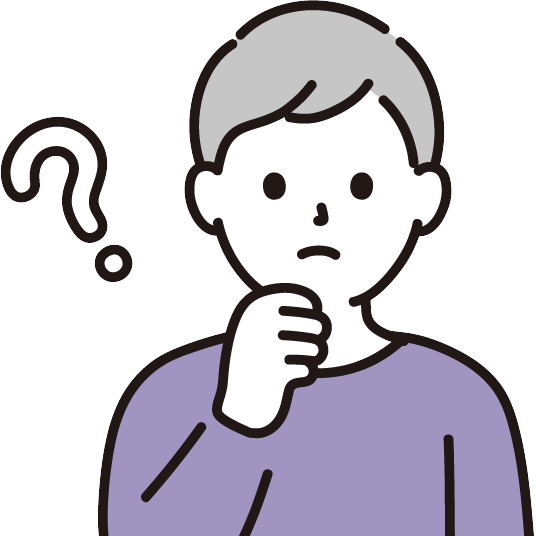
今すぐじゃなくても、何かあったときに家があるっていうのは安心感がありますね。

そうですね。不動産はすぐに用意できるものではないですから、“使える状態で持っておく”というのはひとつの備えになります。
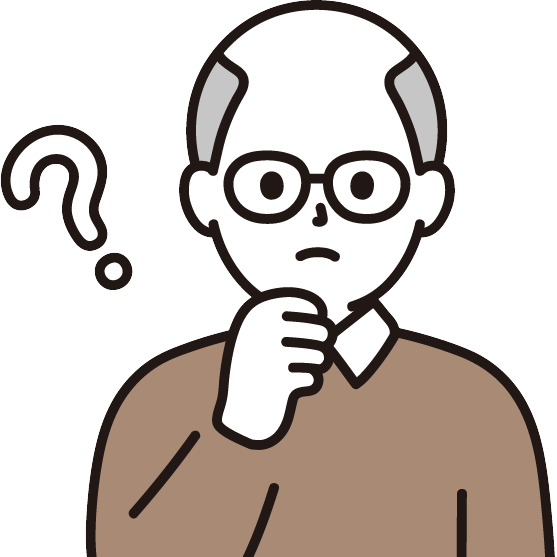
他にも、維持してると何か利点ってありますか?

はい。たとえば、周辺の地価が上がった場合には、売却のタイミングを見て動くこともできます。慌てて手放さなくていい分、市場の動きを見て判断できるというメリットもありますね。
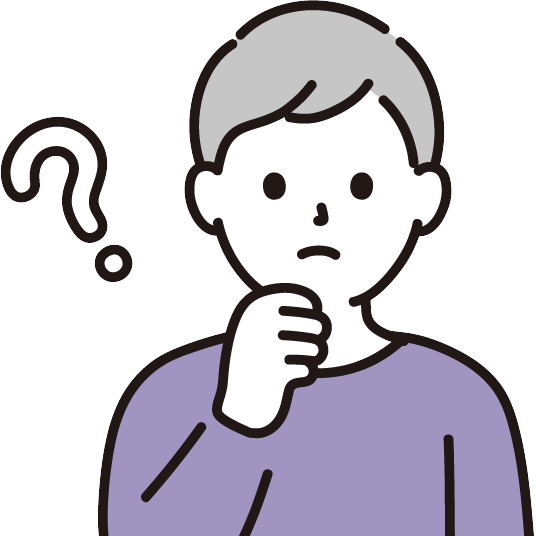
なるほど。今じゃなくても、いずれ売ることも考えられるなら、持っておくのも悪くないのかもしれませんね。

それに、将来的に活用する方向に気持ちが変わったときにも、選べる方法はいろいろあります。たとえば、賃貸に出したり、駐車場にしたりといった使い方ですね。
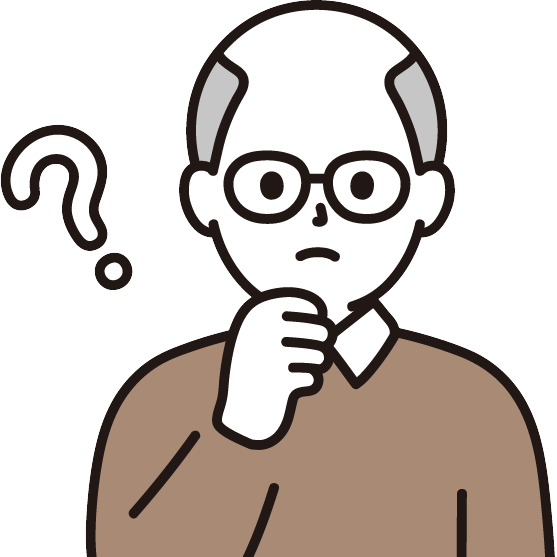
今は活用するつもりはないけど、選べる余地を残せるってことですね。

そうです。“すぐにどうこうしない”という判断も、準備さえしておけば立派な選択ですよ。
まとめ
- 家族が将来使うことができる
不動産を維持することで、将来的に親戚や子供、孫に使わせることができます。家族にとっては、手に入れた土地や家が一生ものの資産となり、代々守っていけるという安心感があります。 - 何かあった時に使うことができる
災害時や自宅のリフォーム時に一時的に住むこともできます。 - タイミングを見て売却できる
長期間不動産を維持していると、市場の動向や自分の状況に合わせて売却するタイミングを見極めることができます。適切なタイミングで売却できれば、大きな利益を得ることができるかもしれません。 - 収益を生む可能性がある
空き家や土地を賃貸にしたり、駐車場として利用するなど、収益化する方法はたくさんあります。定期的な収入があれば、維持費をまかなうこともできます。
注意点
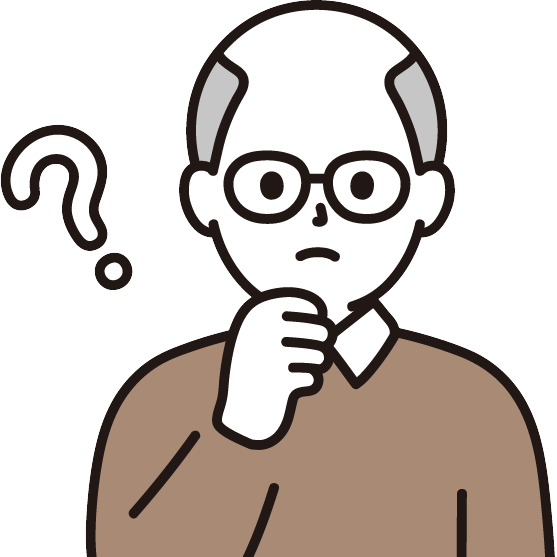
たしかに、選択肢を残しておけるっていうのは安心ですね。維持するリスクはありますか?

はい、いくつか注意しておきたい点があります。たとえば、相続から3年を過ぎると、税金の優遇が受けられなくなるという点です。
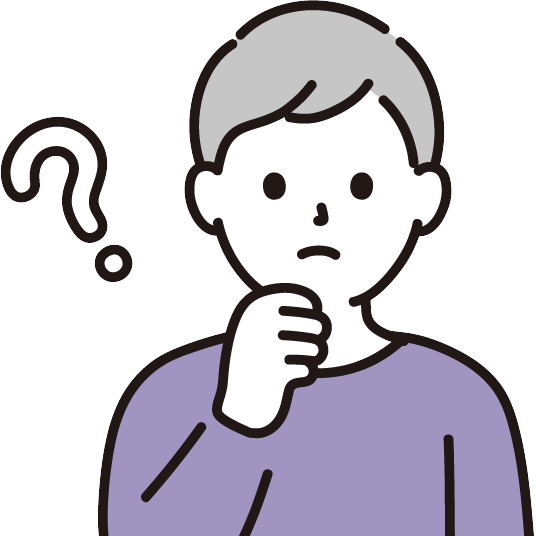
そうなんですか?初めて聞きました。

“相続空き家の3,000万円特別控除”という制度なんですが、一定の条件を満たすと、売却したときの利益から最大3,000万円まで差し引ける制度です。
実際に、当社で相続した不動産を売却された方の半分以上がこの制度を利用して売却されています。
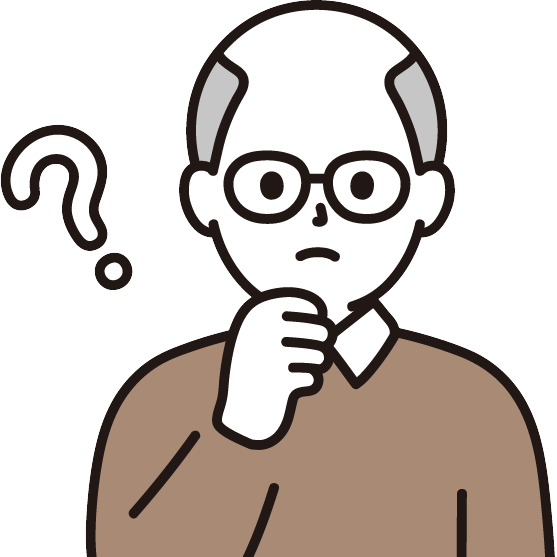
3年を過ぎるとその控除が使えなくなるんですね。
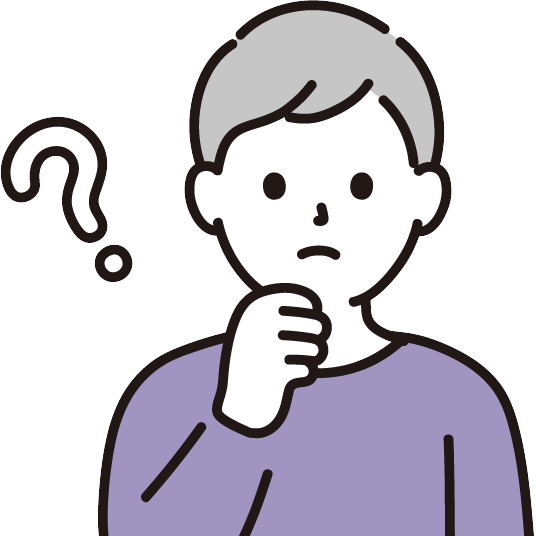
もし、その制度が使えるとどのくらい変わるんですか?

たとえば、相続した家を1,500万円で取得したと仮定して、2,500万円で売ったとします。
利益は1,000万円ですよね。本来ならそこに約20%の税金がかかりますが、この制度を使えば税金がゼロになることもあります。
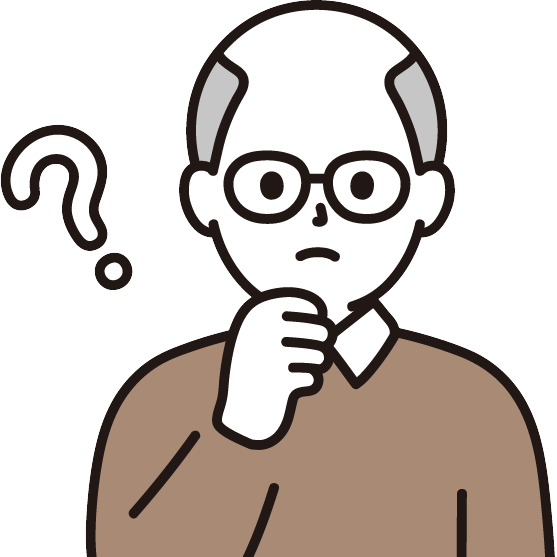
それは大きいですね。でも、期限を過ぎると全部課税対象になるわけか…。

そうなんです。今すぐに売らなくても構いませんが、“いつまでに売れば有利か”という点は、頭の片隅に置いておかれるといいと思います。
まとめ
- 3年を超えると税金の優遇が使えなくなる
相続した空き家を譲渡する場合、「3,000万円の特別控除」や「取得費加算の特例」を活用することができますが、これらは相続から3年以内に売却を完了させないと適用されません。
これらの特例を使うことで、売却益から最大で3,000万円を控除したり、相続税を支払った額を購入価格に加算することができ、税負担を軽減することができます。しかし、3年を過ぎるとこれらの優遇措置は使えなくなるため、早めの判断が重要です。
維持する方法
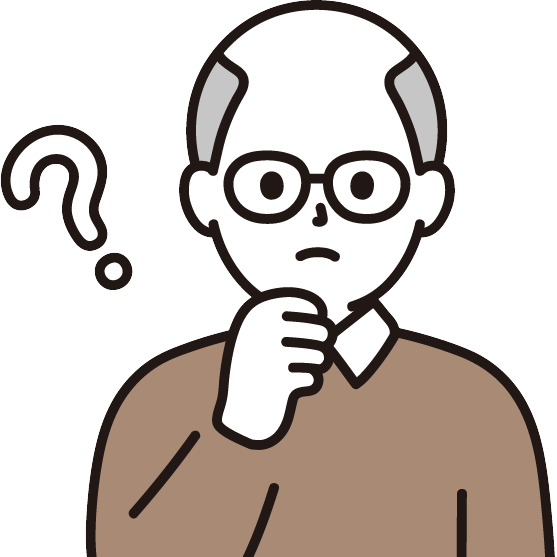
維持するって言っても、実際にはどんなことをやっておけばいいんですか?

はい、大きく分けて3つあります。まずは建物の管理、次に費用の把握、そして将来を見据えた準備です。
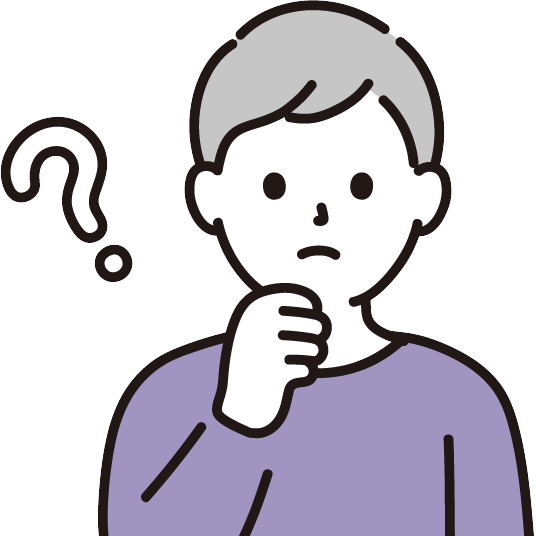
建物の管理って、たとえばどういうことですか?

定期的に建物の状態をチェックすることです。たとえば通風や換気、水回りの通水、雨漏りの確認などですね。あと、庭の雑草取りや、ポストにたまったチラシの処分なども大事です。
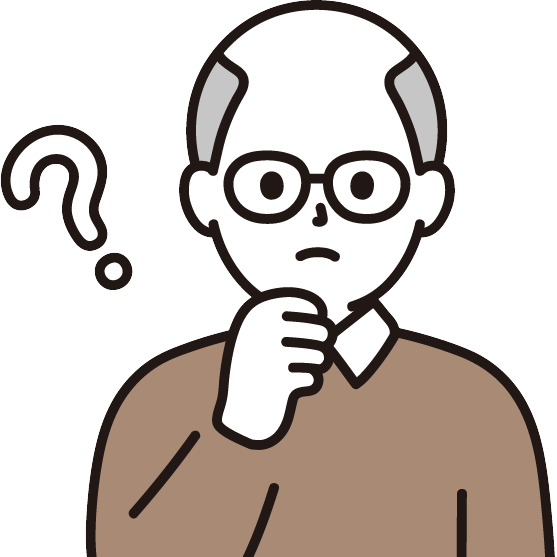
誰も住んでないと、そういうのが全部自分たちでやらないといけないってことですね。

そうですね。ただ、ご自身で管理が難しい場合は、空き家管理サービスをご利用いただく方法もあります。定期的な見回りや簡単な清掃を代行するサービスです。
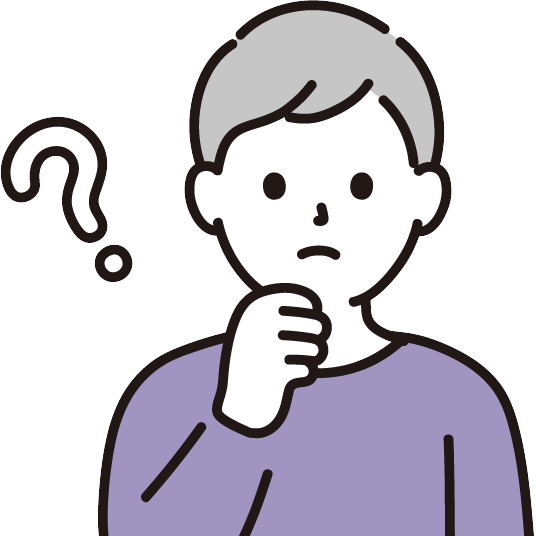
そういうサービスがあるなら、遠方に住んでいても安心ですね。

次に費用面ですが、固定資産税や都市計画税は毎年かかってきます。地域や評価額によって変わりますが、土地と建物で年間10万円前後かかる方が多いです。
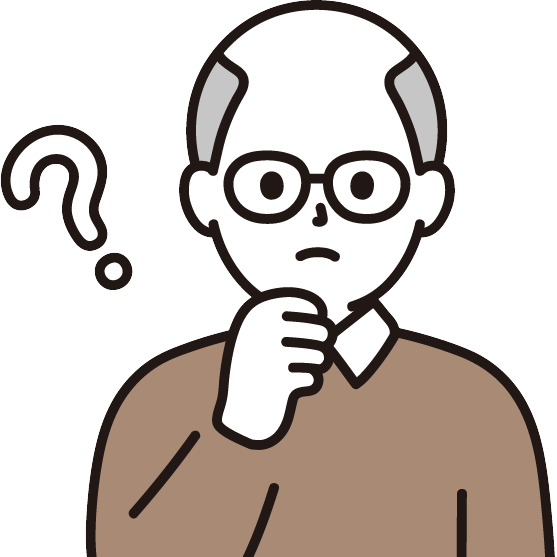
それくらいは覚悟しておいたほうがいいですね。

はい。それと、万が一台風や大雪などで損傷があった場合に備えて、火災保険の見直しもしておくと安心です。
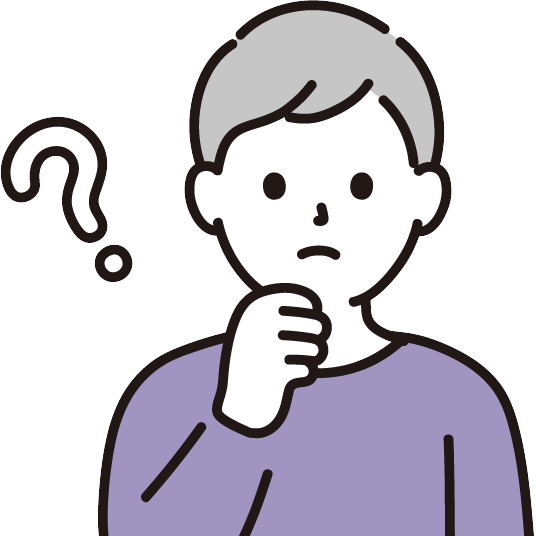
確かに、何かあってからじゃ遅いですもんね。

はい。それと、万が一台風や大雪などで損傷があった場合に備え最後に、将来どうするかまだ決まっていなくても、家族で情報を共有しておくことが大切です。いざというとき、“誰がどうするか”をスムーズに決められるようにしておくと、トラブルも防げますよ。
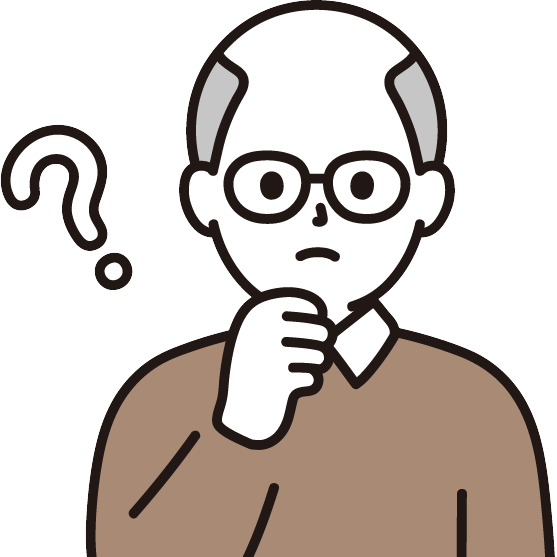
なるほど。思っていたよりやることはありますね。でも、ひとつひとつ聞けてよかったです。
まとめ
- 定期的に建物の管理を行う
- 必要であれば空き家管理サービスを利用する
- 税金・保険の費用を把握しておく
- 火災保険を見直す
- 家族で情報を共有しておく
まとめ
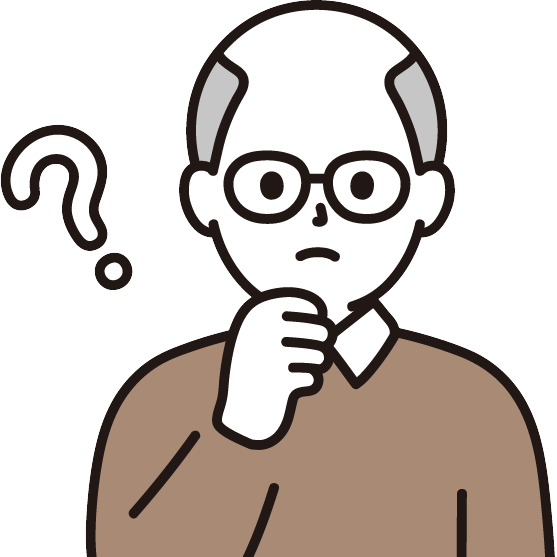
話を聞いてみて、ただなんとなく持ってるだけじゃダメだって分かりましたよ。
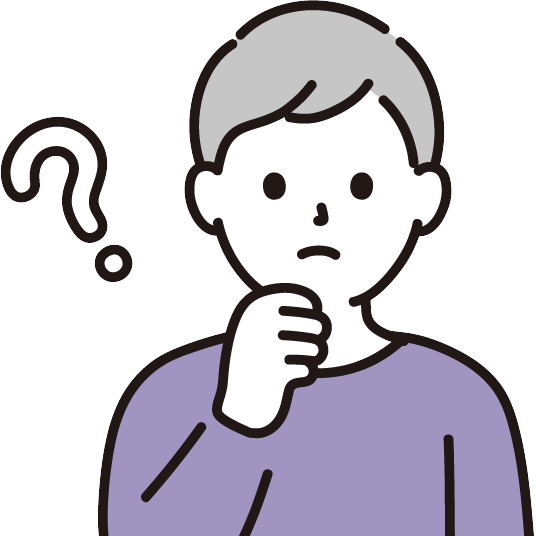
そうね。維持するなら維持するで、ちゃんと管理のことも考えないといけないのね。

はい。持ち続けるという選択も立派な判断です。ただ、そのためには少しだけ知識と準備が必要なんです。
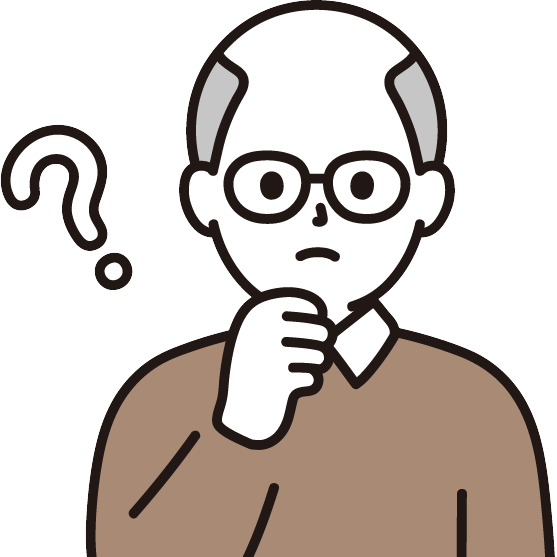
売るかどうかは、まだ決められないけど…少なくとも“持ち方”は考え直さないといけませんね。

そうですね。迷っている段階でも大丈夫です。不安なことや、確認しておきたいことがあれば、いつでもご相談ください。
私たちがお手伝いできること
- 空き家管理サービス
空き家の維持管理をお手伝いします。定期的な点検や清掃、修繕計画の提案を行い、空き家の状態を最適に保ちます。 - 売却のタイミングのアドバイス
いつ売るのが最適かをアドバイスします。市場の動向やお客様のニーズに合わせて、売却のタイミングを見極めるお手伝いをします。 - 維持することがお客様に合っているか?
維持することが本当にお客様にとって良い選択かを一緒に考えます。もし維持が難しい場合は、売却や他の活用方法をご提案します。
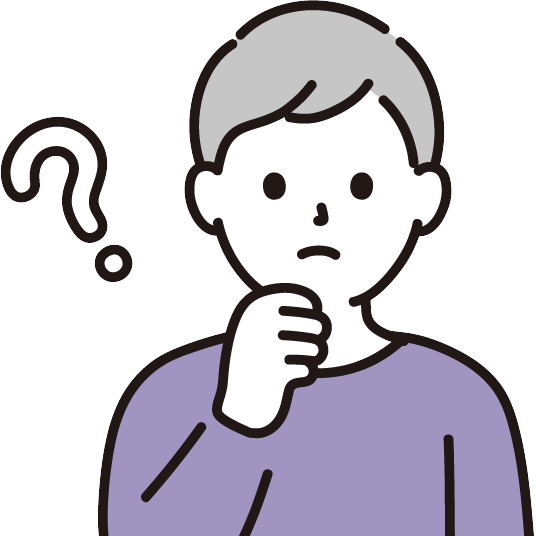
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。
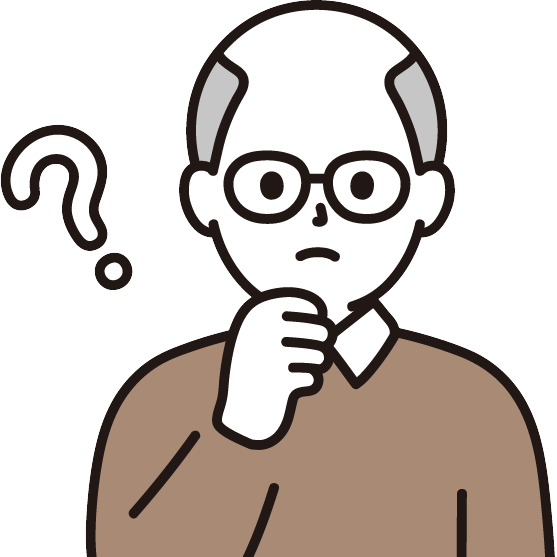
今日は来てよかったです。これからどうするか、家族ともちゃんと話してみようと思います。
株式会社つばきらんどについて
「不動産の売却ってどう進めたらいいの?」「相続した家のことで困っている…」そんなお悩みはありませんか?
当社は、広島市佐伯区・廿日市市を中心に、不動産の売却や購入をサポートしている会社です。
小規模で小回りがきくので、お客様一人ひとりのお悩みに合わせて柔軟に対応できるのが当社の強みです!
おかげさまで、ご紹介やリピーターのお客様が8割を占めており、「話をじっくり聞いてくれる!」といった嬉しいお声をたくさんいただいています(^^)
電話・メールで、どうぞお気軽にご相談ください!
サービスのご紹介