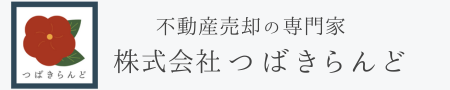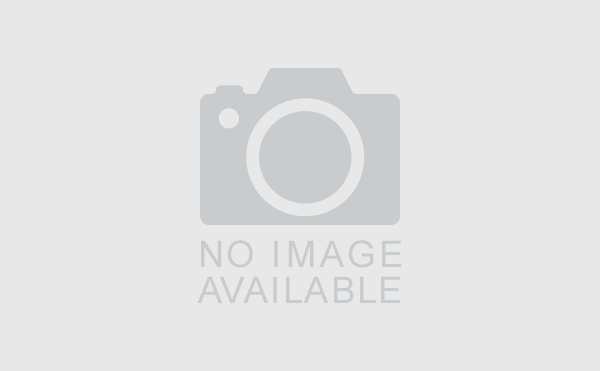【匿名相談】親族間で意見が分かれています。
ご相談内容
はじめまして。父から相続した築40年ほどの実家について、いくつか悩んでいる点がございます。
この物件は現在、親族間で共有しており、今後の管理方法や売却について意見が分かれている状態です。
建物自体は長年使用されているため、老朽化が進み、修繕費用や維持管理費の負担が今後さらに増すことが予想されます。
私を含め一部の親族は売却を希望しているものの、他の親族は実家として使い続けたいと考えており、意見の調整が難航しています。
親族間で意見が分かれている状況の中で、実家を共有している場合の話し合いの進め方や、売却に向けた合意形成のポイントについて、専門家の視点からアドバイスいただければと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ご相談内容の要点
- 実家を親族間で共有している
- 親族間で管理・売却について意見がわかれている
- 修繕費や維持管理費の負担が大きい
- 実家を共有している場合の話しあいの進め方や、売却に向けた合意形成のポイントが知りたい
はじめまして。ご相談いただき、ありがとうございます。
相続されたご実家について、40年という長い歴史のあるお家ですので、思い入れも大きいかとおもいます。
一方で、現実的な維持費や固定資産税の負担も無視できない問題ですね。
共有名義の不動産をめぐる親族間の意見のちがいは非常によくあるケースです。
大切なのは、感情的な対立を避け、冷静に現実を共有しながら“共通のゴール”をみつけていくことです。
■ まずはそれぞれの立場を「理解」することが第一歩です
まず大切なのは、全共有者の立場・希望を把握し、情報をそろえることです。
やるべきこと
- 共有者全員と「今後どうするか」の話し合いの場を設ける
- 物件の現状(老朽化、固定資産税、修繕費などの負担)を客観的に共有
- 固定資産税評価額や市場査定など「資産価値」の情報も提示
■ 話し合いを円滑に進めるためのポイント
① 第三者の専門家を交える(冷静な進行役として)
共有者だけで話すと感情的になりやすいため、不動産会社・司法書士・弁護士などを間に入れることで、話がスムーズになることが多いです。
特に「相続に詳しい不動産会社」や「共有不動産に強い弁護士」は、中立的な立場で提案や助言をおこなうことが可能です。
② 「使いたい人」と「売りたい人」の間の“落とし所”を探る
意見が分かれる場合は以下のような選択肢も検討されます:
| 状況 | 検討される選択肢 |
|---|---|
| 一部が使用を希望 | 他の共有者の持分を買い取ってもらう(持分買取) |
| 修繕が困難・空き家状態 | 賃貸化または売却により費用負担をなくす |
| 将来的に使う可能性が低い | 一定期間は保有し、その後売却する合意(期限付き保有) |
| 管理・費用負担が不公平 | 「管理契約」を作って負担を明確にする |
■ 売却に向けた合意形成のステップ
① 全員で物件の査定を受ける
→「実際いくらで売れるのか?」を知ることで、現実的な判断がしやすくなります。
※できれば第三者性のある不動産会社に依頼(机上査定・訪問査定)
② 共有者それぞれの意見とリスクを整理する
→固定資産税の負担、空き家放置による劣化リスク、法改正による管理責任など
③ 売却後の資金配分案を提示
→売却代金をどう分けるかが見えることで、「売ってもよい」という人が出てくる可能性があります。
④ 「どうしても売却に反対する人」への代替案提示
→感情や想い出が強い方には「一時的な保存」「記録を残す(写真や動画)」など、気持ちの整理を促す工夫が有効です。
■ それでも意見がまとまらない場合は...
① 持分売却という選択
どうしても合意がとれず、ご自身だけでも身軽になりたい場合、「持分のみを第三者に売却する」ことも可能です。
ただし、持分だけを買う人は少ないため、価格が相場より下がる傾向があります。また、第三者が共有者になると人間関係が複雑になる可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
② 共有物分割請求という法的手段
最終手段として、「共有物分割請求(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう)」という裁判手続があります。
これは、共有状態を解消するために裁判所を通じて不動産の分割(売却や現物分割)を求める手続です。
話し合いが完全に行き詰まってしまった場合に限りますが、法的に不動産を売却して、代金を共有者で分けるよう命じてもらうことも可能です。
■ まとめ
実家を親族で共有していると、「どうするのが正解なのか」と悩む場面も多いかと思います。
ご家族それぞれに思いがあり、簡単に答えが出ないのが自然です。
だからこそ、まずは現状を共有し合い、少しずつ方向性を探っていくことが大切です。
お話が行き詰まりそうなときは、無理に結論を急がず、専門家の力を借りて冷静に話し合える環境を整えてみてください。